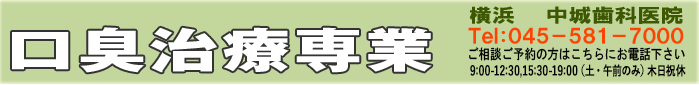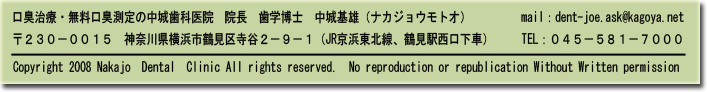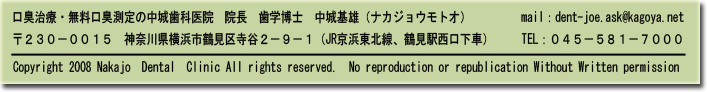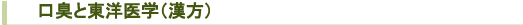
私、中城は歯科医として25年程、患者様と接して参りました。
その中で気付いたのが、「虫歯治療」「歯周病治療」といった治療では
どんな方でも同じ治療をすれば同じような効果が得られました。
しかし、「口臭治療」についてはそうではありませんでした。
症状が同じに見えても、ある患者様は数回の治療で劇的な
効果が得られ、またある患者様は何回治療をしても思うような
効果が得られませんでした。
そこで、口臭のお悩みには、「個人の体質」が深く関係しているかもしれない
と考え歯科医療のかたわら、39歳にして再び針灸治療の夜間部専門学校に
3年間通い、東洋医学の道に入ったことが、口臭治療を専門として実施する
きっかけとなりました。
そして、東洋医学を勉強していくと、東洋医学にも臭いの分類があることに気付きました。
下の表が臭いの分類表です。
この分類を口臭治療に役立てることはできないかと考えました。
東洋医学は人の体質を「気」「血」「水」の3つで捉えます
臭いの分類表を見ると、東洋医学は難しいと思われますが、実はシンプルです。
東洋医学は人の体質を「気」「血」「水」の3つで捉えます。
下のイラストは「気」「血」「水」のイメージです。
気
鍋に穴が開いていないか?スイッチが壊れていないか?全体のシステムが正しく作動しているのかを、気を張って全体的に、 管理している部分が、『気』
血
鍋を温める部分が、血流の『血』
水
鍋の中の湯が、体液に相当する部分が『水』
この『気』『血』『水』の増減によって、体質が変化します。
これらの変化は、身体の随所に、見て解る変化として現れます。
東洋医学は、舌診と脈診をとても重要視します。
舌の性状と口臭のとの間には、密接な関係があります。
舌の症状でこんなことが分かります。
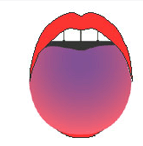
- 【紫色】
典型的な所見として、目の下のクマの色、爪や唇や舌の色が紫舌に変化する所です。この体質の方は、末梢循環不全になりやすく、歯肉の色も「どす黒く」変色してきます。
血行不良により、普段から歯肉に微細な炎症を抱えがちで、歯周病菌が増殖しやすく、口内環境のバランスが、口臭発生菌優位の状態になります。
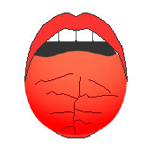
- 【シワ(裂紋)】
典型的な所見は、舌がひび割れてきて、舌の先の方から赤く変色してくる。この体質の方は、身体の水分が少なくなるので、例え穏やかに火が燃えていても、相対的に身体の中が、「空だき状態」に傾きます。すると、燃やす火力は穏やかでも、結果的に熱化してきます。
舌の状態も全体的にしぼんできます。ちょうど、舌が「干し椎茸」の様に変化するのですね。
こうなると、口が渇き、唾液の分泌量が低下するので、歯肉の粘膜に唾液蛋白の膜がなくなり、やはり細菌感染や歯周病菌が増殖し、口臭が発生します。さらに、舌の表面の味を感じる細胞が萎縮するので、味覚異常も起きます。
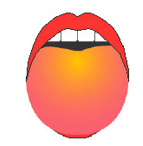
- 【黄色】
典型的な所見は、舌の中央より奥の方に、ネバネバした黄色い苔が付着してきます。こうした変化は、例えば、暴飲暴食をしたり、二日酔いの翌日の朝、洗面所でアカンベーをした時に見られます。(思い当たる方も多いのではないでしょうか?)
胃腸に過度の負担をかけると、「胃熱」が発生し、「痰湿熱」に移行します。この黄色い舌苔は、特に、揮発性臭気物質の温床であり、口臭の中でも、重度の傾向を示すので、注意が必要です。
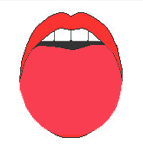
- 【赤色】
典型的な所見は、舌の先を中心として、全体が赤く変色してきます。
進行すると時として赤黒くなる時もあります。�こうした変化は、舌だけでなく、身体の随所に現れます。例えば、頬の赤ら顔、赤目や耳たぶの色、お小水が黄色く変色、手の平が赤くなります。
舌の色が赤ければ赤い程、口臭レベルも上昇しがちです。口腔内の変化で言えば、歯槽膿漏に罹患しやすくなり、年中、口内炎が出来ます。また、口の中が渇いて、喉の奥もしみたりしてきます。
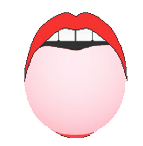
- 【白色】
典型的な所見は、舌の横腹が歯の形併せて、ギザギザ・デコボコしてきます。また、お疲れモードにはいると、身体の働きが機能低下を起こすので、血のめぐりが悪くなり冷え性を呈する事から、舌全体が白っぽく変色してきます。
こうした変化は、舌だけでなく、身体の随所に現れます。
例えば、顔色も合い白くなります。
声に力が出なくなり覇気が感じられなくなります。
その他、直ぐに横になりたがったり、容易に風邪を引いたり、下痢しやすくなります。
1.ドロドロ血流タイプ…お血型
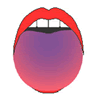
鑑別点は、「紫」
●随伴項目:青あざ、血腫、クモ状血管、目のクマ、爪紫色
●口腔領域:歯肉の色が、紫→どす黒い→審美治療に
2.カラカラ乾燥タイプ…腎虚型
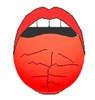
鑑別点は、「裂紋」
●随伴項目:のぼせ、火照り、 不眠、瞼のけいれん、膝・腰痛
●口腔領域:口渇、舌の灼熱感、ヒリヒリ感、舌痛症、義歯難症例
3.ネバネバ湿化タイプ…痰飲型
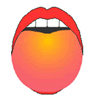
鑑別点は、「黄」
●随伴項目:ゲップ、倦怠感、鼻水関節痛、痰がらみ、喉のつかえ感
●口腔領域:口の粘つき、舌苔付着、唾液粘張度↑ 味覚障害
4.カッカッ熱化タイプ…胃熱型
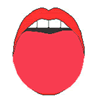
鑑別点は、「赤」
●随伴項目:目赤、赤ら顔、赤い掌、鼻尖・眉間も赤、声が大きい、短気
●口腔領域:歯肉炎、口内炎、口渇、舌痛、歯周病、インプラント予後不良
5.ブヨブヨ浮腫タイプ…水滞型
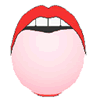
鑑別点は、「白」
●随伴項目:慢性疲労、むくみ下痢、頭重、鼻水、悪心、嘔吐
●口腔領域:歯肉の浮腫、白い苔、唾液がアワアワ、マージンが合せにくい
※表示されている臨床例は、患者さんからの了解を得て、開示しています。
症例1. 熱化型
ガス濃度(ppb)測定日ごとの推移グラフ
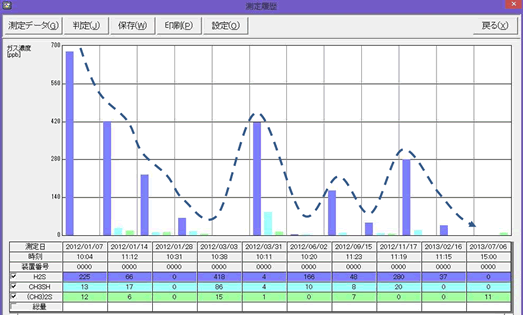
- 推奨漢方処方:治胸散加ワグラスD
- ※漢方薬は、オリジナルレシピに基づくものです。市販では扱っていない処方になります。
症例2. 湿化型
ガス濃度(ppb)測定日ごとの推移グラフ
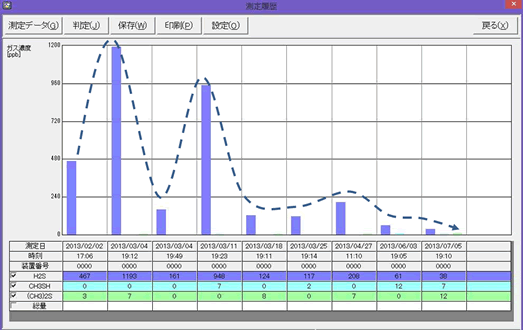
- 推奨漢方処方:六君利気散加痰飲散
- ※漢方薬は、オリジナルレシピに基づくものです。市販では扱っていない処方になります。
症例3. 乾燥型
ガス濃度(ppb)測定日ごとの推移グラフ
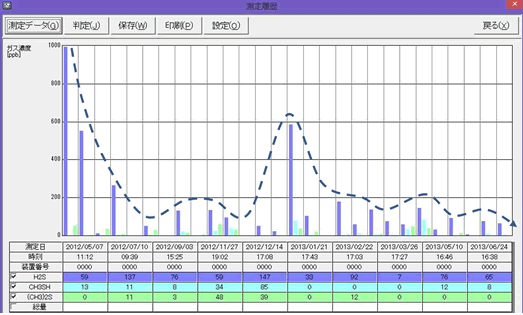
- 推奨漢方処方:ダイギャク粒加アンセイ粒
- ※漢方薬は、オリジナルレシピに基づくものです。市販では扱っていない処方になります。
症例4. お血型
ガス濃度(ppb)測定日ごとの推移グラフ
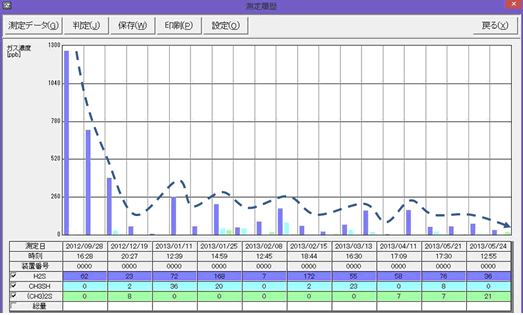
- 推奨漢方処方:チョウケイ粒加通経散
- ※漢方薬は、オリジナルレシピに基づくものです。市販では扱っていない処方になります。
症例5. 水滞型
ガス濃度(ppb)測定日ごとの推移グラフ
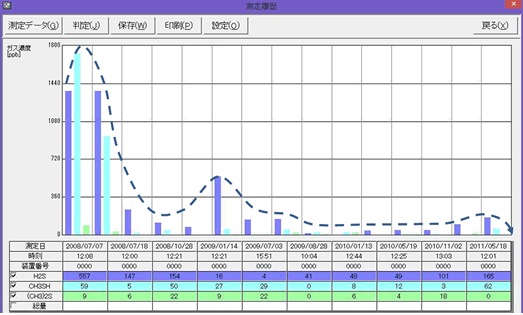
- 推奨漢方処方:痰飲散加エンピーズ
- ※漢方薬は、オリジナルレシピに基づくものです。市販では扱っていない処方になります。